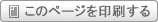若かったあの頃
「ご飯出来たよー。」と叫ぶ声がする。
その声の主は祖母だ。私は生まれて間もなく祖母に育てられた。母親の顔は知らない。
祖母以外の家族の顔を知らずに育った。これが日常の光景。平凡な二人暮らしの家族の食卓の時間だ。
テーブルの上にはいつも白いご飯、漬物、魚、おさしみ、決まってこのメニューだ。
祖母は料理が苦手だと言うことは誰が見てもすぐにわかる。
それでも、一生懸命用意してくれた。まだ、ありがたみの知らない幼い私は、文句を言う。「えーーーまたこれ?もっと違うの食べたい!カレーとかハンバーグとか!給食には出るのに何でおばあちゃんは作ってくれないの?」いつも変わらず私の文句を笑って聞いている祖母。大抵のことでは怒ったりしない温厚な人だ。それをいいことに私は不満だけを毎日毎日ぶつけていた。
そんな日々が続いたある日のことだった。庭で遊ぶ私の鼻に嗅ぎ慣れない匂いが届いた。祖母は私のためにカレーを作ってくれていた。その夜の夕食はカレーだった。当時72歳の祖母が昼間からずっと台所に立って作ったカレーだ。テーブルに置いてあるカレーを一口食べた。美味しいとはかけ離れたものだった。じゃがいもとにんじんは一口では入らないくらい大きくて固く、玉ねぎではなく、長ネギが入っていて、肉なんてものを買わない祖母は秋刀魚の缶詰を入れていた。ルーは溶けてなく、具と同じくらいの塊になっていた。
一口で食べるのをやめた私に祖母は、「美味しいものを食べさせられなくてごめんね。」とそっとつぶやいた。そして私にはふっくら炊き上がった白いご飯と漬物、魚、おさしみが並べられた。すまなそうな顔をして一人カレーを食べる祖母。その後も夜中にひっそりと、カレーを「美味くない」と言いながら、食べていたのを覚えてる。
あの頃は素直になれなかったけれど、本当はとても嬉しくてありがとうと言いたかった。
あの頃から17年の月日が流れ、私も料理をする年齢になった。病気がちな祖母は、味のついた食事が食べられないほど年老いてしまった。
今は離れて暮らしているが、たまに帰ってご飯を作ってあげると涙を流しながら食べてくれる。「こんな美味しい料理食べたことない」と言いながら。
味などついていないのに。そんな祖母の姿に私も涙を流してしまう。あの頃は祖母の気持ちがわからなかったけど、今なら痛いほどわかる。「おばあちゃん、ありがとう。おばあちゃんが用意してくれたご飯でこんなに大きくなりました。」あの日を思い出しながら、祖母を思い出しながら今日も料理を作る。
愛する新しい家族のために。