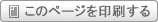おにぎりは幸せの香り
昨夜の激しい空襲で一晩中逃げ廻った私達は空が白み始めた頃、足を引きずって家路についた。しかし、家のあった場所は一面の焼野原と化していて、ただ庭の石灯籠だけがゴロンと倒れていた。爆撃の下にすべてをなめつくされて私達家族は、何をする気力も失っていた。気が付けばいつの間にか太陽はギラギラと容赦なく頭上を照りつけていた。
母はふと何かを思い出したように台所だった場所に走って行き、煉瓦の下から黒こげの鉄のお釜を掘り出して来た。それを大切そうに抱えて来て私達の前に置いた。父と子供達が輪になってお釜の中を覗いてみると、どうだろう。中には目もくらみそうな真っ白なご飯が入っていたのだ。ふっくらとして、しかもまだ少し温かい。胸に広がるふんわりと甘くなつかしいご飯の匂い。兄妹達はかわるがわるお釜を覗いては出来るだけ深く匂いを吸い込もうとしていた。
これは確か田舎のおじさんが命がけで家まで運んで来てくれたお米だった。それを、いつ空襲になるかも知れないので早く食べてしまおうと母が研いでおいたのが、火事ですっかり炊き上がってしまったらしい。お釜のすぐ内側はキツネ色にこげていたが、そこがおいしそうで思わず唾を飲み込んだ。
母はいつもの主婦の顔にもどり、ドブ板をはずして中にかくしておいた梅干と塩を取り出しせっせとおにぎりを握り始めた。握るそばから待ちかねていた家族の手の平に置いてまわった。暑さも忘れてピカピカのおにぎりを立ったまま頬張った。お皿もテーブルも何もない。今夜泊まる所さえないというのに私達は手の平の雪のように白い香りに浸っていた。涙がこぼれそうな幸せな朝だった。
私は今でも梅干のおにぎりを日曜日の朝の遅い食事に出す。平和な光の中で子供達はテレビを見ながら無心に食べている。焼跡で立ったまま涙を浮かべておにぎりにかじりついていた子供のことなど誰も知らない。