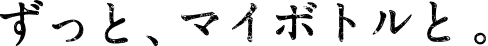COLUMN
2020.01.30
SpecialCOLUMN
未来へつなぐ、私のバトン
山間の実験の場から世界へ。 共創による社会の仕組みづくりを。
NPO法人 ゼロ・ウェイストアカデミー 理事長 坂野 晶

徳島県上勝町。人口1500人ほどの小さな自治体がここ数年、世界中から注目を集めている。町への視察者は年間1000人以上。取り組んでいるのは「ゼロ・ウェイスト」という、ごみを極力減らし、なるべく資源として循環させるという活動だ。SDGs(国連が2015年に定めた17の持続可能な開発目標)やサーキュラー・エコノミー(循環型経済)など、サステナブルな社会の実現に向けた動きが昨今加速しているが、上勝町では10年以上前となる2003年からこの活動を続けている。
そして、2019年1月。世界経済フォーラム(WEF)の年次総会、通称「ダボス会議」で若き日本人女性が共同議長を務め、一躍脚光を浴びることになる。上勝町を拠点に活動するNPO法人ゼロ・ウェイストアカデミー理事長、坂野晶さんだ。
そんな坂野さんが立ち上げた「ゼロ・ウェイスト認証制度」でパートナー認定の第一号となったのが、象印の「給茶スポット」。その採択理由とともに、上勝町での活動の内容やその背景にある想いを伺った。
絶滅の危機に瀕する鳥が、環境問題を教えてくれた
環境問題に関心を寄せたきっかけを尋ねてみたところ、聞き慣れない鳥の名前が返ってきた。
「小さい頃から鳥が好きだったんですが、10歳のときに読んでいた本で、「カカポ」という、ニュージーランド固有種のオウムのことを知りました。世界で一番大きな飛べないオウムで、おもしろい鳥なんですが、その本の最後に、このままだとこの鳥は、森林伐採や外来種の持ち込みといった人間の活動が原因で絶滅してしまうと書かれていたんです。それがすごくショックで。そこから絶滅危惧種、そして環境問題に関心を持つようになりました。」

「それから、環境問題に取り組む仕事って何があるんだろうと調べたんです。海岸でごみを拾う、植林をするなどの活動はよくありますが、それらはあくまでもボランティアであって、仕事ではない。それに、すでに起こっている環境問題への対応策であるとは思うんだけど、根本の原因解決策ではない。そんなモヤモヤも同時に抱えるようになって、どうしたらいいんだろうと考えはじめたんです。」

社会の仕組みをデザインする
「最終的に行き着いた答えが、社会の仕組みそのものを変える必要がある、ということ。マインドを変えるには限界がある。根本的な課題に取り組むには、人々のアクションを変える仕組みのデザインが必要不可欠だ、と。そんな思いから大学では環境政策を学びました。しかし、そこで感じたのは、理想の法律やルールを描くことはできるけれど、それを現実に実行していくのはとても難しいという、現場との乖離でした。」

「どうすれば理想に近い状態で仕組みづくりをしていけるんだろう。悩んだ結果たどり着いたのが、トライアンドエラーで政策の実行と検証を繰り返していかないといけない、というひとつの答えで、それが今の活動のような、特定の地域で実証実験をするという取り組みにつながっていきました。」

活動の舞台、上勝町
生活者の意識や行動を変えるのは大変で、企業や生産者を動かすというのも難しい。根本的な課題解決のためには、より全体として、視座を上げて、仕組みをデザインしていく必要がある。トレードオフになりがちで、遠目から指摘しているだけだと何も変わらない環境問題においては、変えていけるところから着実に変えるということが大切なのだと坂野さんは語る。そして、その舞台となったのが、徳島県中部にある山あいの町、上勝町だ。
「上勝町は、1990年代後半から、焼却に頼らないごみの処理・分別に取り組んでいる珍しい自治体です。小さな町なのでお金がなく、焼却炉も作れない。他市町村に送って燃やしてもらうにも大きな輸送コストがかかる。他の自治体以上にごみ処理の課題と真剣に向き合わざるを得なかったんです。」

日本初となる「ゼロ・ウェイスト宣言」
上勝町は2003年、2020年までに同町のごみゼロを目指す「ゼロ・ウェイスト宣言」を日本で初めて行った。
「『ゼロ・ウェイスト宣言』というのは、オーストラリアの首都キャンベラが世界で初めて行った、目標年までにゼロ・ウェイストを目指すという宣言です。宣言には、2020年を目標に、焼却・埋め立てせざるを得ないごみをできるだけ減らす。そのための人づくりに力を入れていく。世界中に同じような仲間をつくる、という、大きく3つのテーマが存在します。それらを上勝町の行政だけで進めていくには限界がある。フレキシブルに取り組みを先導する民間組織が必要だ、ということで、2005年に『NPO法人 ゼロ・ウェイストアカデミー』が立ち上がりました。」

上勝町との出会い。ゼロ・ウェイストアカデミーへの参画
ごみの分別はなんと45種類。リサイクル率は全国平均の4倍となる80%以上を誇る上勝町。そんな町と坂野さんの出会いは大学時代に遡る。
「たまたま大学の同期に上勝町出身の子がいて、おもしろい地域だな、とは思っていたんですが、足を運んでみて驚きました。上勝町では、自分ごととしてごみ問題の大事さを語れる人がとても多かったんです。行政関係なく、一般人の主婦や、おばあちゃんまで。そういう意識を持った人がたくさんいるからこそ、こういった仕組みが成り立って、ちゃんと続いていくのかもしれないな、と可能性を感じましたね。」
大学在学中、国際学生団体「アイセック」の活動でモンゴルに渡った坂野さん。モンゴル支部の代表として活動した後、国際物流大手のフィリピン法人で2年間働いた。帰国後、先ほどの友人に誘われ、興味のあった上勝町に身を置いていたところ、過渡期を迎えていたゼロ・ウェイストアカデミーを手伝うことになり、そのまま移住を決意。2015年11月から理事長を務めている。

日本中を飛び回り、活動を広げる
「ごみステーションの管理・運営など、一般廃棄物の中間処理業務のほか、様々な周辺施策やプロジェクトの推進に関わっています。今日のような形で、市民団体や自治体関係、地域の環境政策を行なっている外部団体などに招かれることも多く、そこで活動や取り組み内容をお話しすることで、活動の輪を広げています。」
取材当日は、世界140ヶ国に拠点を持つCircular Economy Club(CEC)の東京支部がオーガナイズするワークショップイベントに招かれ、登壇。ダボス会議以降、引き合いも大きく増え、日本中を忙しなく飛び回っている。

「ハードルが高すぎるという理由で、企業には当初敬遠されていた部分もありますが、最近ではそういった企業やお店との取り組みも徐々に始まっています。『こういう取り組みを始めました!』とか『ごみになるものの無駄づかいをやめました!』とお声がけいただくことが増えて、嬉しいですね。活動を通じて、着実にいい方向に変わっていく瞬間を感じています。」
自身が中心となる形で、この日登壇したCircular Economy Clubの関西支部立ち上げも計画しているという坂野さん。今後の活動がますます楽しみだ。

「給茶スポット」が「ゼロ・ウェイスト認証制度」パートナー認定の第一号に
坂野さんが活動の一環として立ち上げた「ゼロ・ウェイスト認証制度」。そのパートナー認定第一号に象印の「給茶スポット」が採択されたことから、象印との関係は始まる。
「ごみの課題に取り組むとなると、消費する側の生活者と、生産・提供する側の企業との『間』がすごく重要で、そこにひとつ当てはまるのが『お店』なんじゃないかと思っています。」

そこで坂野さんが立ち上げたのが、お店がどれだけごみを減らせるかという思いをもとにした『ゼロ・ウェイスト認証制度』だ。一個人が商品選択を変えるよりも、お店が仕入れ先を変えることのほうが生産企業側へのインパクトは大きく、お店のフィロソフィーもお客さんに伝えられ、環境問題への意識の啓蒙にもなる。
「生活者と企業との中間に位置するお店だからこそ、企業と個人の両面に影響を及ぼせるはずだと思ったんです。まずは飲食店から活動を始めました。飲食店向けの認証項目の一つに"BYO(Bring Your Own)"、つまり、容器や食器なんかをお客さんが持ってくることによって減らせるごみってあるよね、という内容があって。その代表格がマイボトルなんです。そういう取り組みを加速していくような企業を認証のパートナーとして推薦できたらなぁと思っていたんです。」

マイボトルを持ち歩く、行動のハードルを下げていく
象印が2006年から続けていた「給茶スポット」の取り組みが、坂野さんの想いにぴったりとはまることになる。
「『給茶スポット』と書いてくれていると、わかりやすくて声をかけやすい。可視化によって心理的ハードルが下がりますよね。自分の容器を持ち込むという行動へのハードルを下げていくことが重要なんだと思います。容器ごみを減らすための理想は自分で持っていくことですが、まだまだ意識が浸透していなかったり、衛生管理の面で課題があったりと、ハードルが高い。ただ、大規模展開は厳しくても、個人商店レベルでなら地道に取り組むことができる。昔の豆腐売りや、しょうゆの量り売りみたいな、そういう仕組みを少しずつ広げていくイメージですね。量り売りだと、欲しい量だけ買えるので、フードロスの問題にも応えることができます。ヨーロッパなどでも無料給水スポットといった取り組みは進んでいますし、スーパーなどの小売店では量り売りも徐々に始まっている。そういう流れを日本でも作っていきたいですね。」

意志表示の象徴にもなるマイボトル
「マイボトル浸透の大きな課題って、中身がなくなったときに飲み物を補充できる場所が少ない。しかも重くて荷物になる。だからわざわざ持っていかない、となっちゃうことだと思うんです。オフィスのウォーターサーバーや給湯室を活用すれば意外とクリアできたりするんですが、それでもなかなか広がらない。給茶スポットはその課題に応えようとしている取り組みですよね。」

坂野さんはもうひとつ、マイボトルのいいところを教えてくれた。
「マイボトルって、目立つし、わかりやすいアイコンだと思うんです。机の上にわざとらしく置くだけで、『あっ、この人はこういう考えの人なんだな』ってことが伝わるじゃないですか。環境問題への意識って、内面的な部分が多くて、見える化されにくいんですが、マイボトルは見ればすぐ伝わる。そういう自分の意志表示としての側面もいいところですよね。」

イノベーションを起こすには、みんなの力が必要
課題が複雑に入り組む環境問題だが、最近は裾野が広がっているという。
「これまでは、生産者、生活者、廃棄物の回収業者、自治体など、関係者それぞれが乖離していたように思います。でも最近はちょっとずつ、こうした人たちが同じ方向を向き始めた。仕組みづくりの中に、クリエイターやテクノロジーも入り始めていて、イノベーションやソリューションが生まれる素地のようなものが少しずつできてきているように感じています。」
確かに環境問題は、一アクターだけでは解決できない難しい課題だ。
「国連や政府レベルの高尚な話と、身近な主婦の行動の話というように、話が両極端になりがちなんですよね。でも、これからはまさにそういう、生産、素材開発、サプライチェーン、小売、回収といった、これまで分断されていた様々なレイヤーの人たちを巻き込んだ共創が必要で、そのための実験の場が求められているんだと思います。」

「ゼロ・ウェイスト」は不可能を可能にする
「この活動をやっていると、『ごみをゼロにすることなんて無理じゃないか』という声を聞くことがあります。でも私は、『ゼロ・ウェイスト』とは不可能を可能にする目標なんだと思っているんです。50%を目指しましょうという目標だと、永遠に60%になることはないですよね。確かに完全なゼロにはならないかもしれないですが、極端なことを目指すと、その目標に向けてとことん検討を突き詰めることができる。それこそSDGsでよく言われる『ムーンショット』や『バックキャスティング』も同じですが、そういった極端な目標を設定し、それを実現させるための抜本的なアイデアを設計していくことでイノベーションって生まれるものだと思うんです。」

ちょっと立ち止まって考えてみるだけで、ごみは減らせる
坂野さんは最近、ごみになってしまうものをどうやって助けるかを子どもたちと考えるカードゲームを開発したという。
「ごみの3R(リデュース、リユース、リサイクル)という言葉がありますが、リフューズ(断る)という項目がゲームにはあって、そもそも使わない方法を考えよう、と。すると、子どもたちからもクリエイティブなアイデアがどんどん出てくる。日常の中では、思考停止してしまっていて、簡単でラクな選択肢につい流されてしまいがちなだけなんです。ちょっと立ち止まって考えてみるだけで、ごみは減らせると思うんですよね。」

「個人的には、自分は怠惰な人間だと思っているんですよ。こんな活動をしていますが、別にプラスチックごみをまったく捨てていないわけではないですし、どちらかというと一般的な人の感覚に近いと思っています。めんどくさいと感じることもあれば、やりたくないと思うこともある。だからこそ、その一般的な視点に立った上で、これからも社会の仕組みづくりを考えていきたいんです。」

*プロフィール、本文等、内容については2019年11月取材時のものとなります。