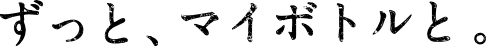COLUMN
2020.09.01
SpecialCOLUMN
未来へつなぐ、私のバトン
地域に根ざし、地域と学び合う。サッカークラブFC大阪が実現するSDGs。
FC大阪 会長兼理事長 吉澤 正登

来季のJリーグ加盟が期待され、サッカーファンや地元サポーターから熱い視線が注がれているFC大阪。実は近年、別の角度からも多くの注目を浴びている。数年前から、全国のプロサッカークラブの中でも先駆けてSDGsの概念をクラブ運営に取り入れ、積極的に活動を繰り広げているからだ。
この取り組みを牽引するのが、自身の経営する企業内のサッカーチームを母体にFC大阪を立ち上げた、会長兼理事長の吉澤正登さん。FC大阪のホームタウンである東大阪市だけでなく、大阪府を始めとした多くの自治体や企業、さらには大学とタッグを組み、選手らを巻き込みながら地域に根ざしたSDGsに関わる活動を次々と行っている。象印も連携企業のひとつだ。
なぜサッカークラブがSDGsなのか、さまざまな連携先と組みどのような取り組みを行っているのか、象印とは何をコラボレーションしていくのか......。吉澤さんの半生も振り返りながら、多岐にわたり伺った。
ブラジルで見たサッカークラブと地域の関係性
吉澤さんのサッカーとの出会いは、小学校就学前。以来、夢中でボールを追う日々だったが、当時は少年の間で野球が盛んだった。
「野球をやっている友達が多く、いくらでも野球にスイッチするチャンスはありましたが、坊主頭にしたくないという思いからサッカーひと筋の学生時代でした(笑)」
サッカーと言えば、ブラジル。肌で感じてみたい想いから、ブラジルに渡る。
「驚いたのは、多くの選手達が"自分が活躍することで出身地域を豊かにしたい"、"自分の活躍で、貧しい子ども達に夢を与えたい"といった、地域に対する思いを抱いていたこと。実際に、地域からスター選手が出たらお金が落ちて、地域の経済状況まで変わるという現実がありました。だから、地元の人たちも単なるエンターテイメントを楽しむ以上の熱量で、選手やクラブを応援していた。そんな地域と密接したサッカークラブの姿が、ブラジルにはありました。」
ブラジルにおいて目で見て肌で感じたサッカークラブの社会的意義は、のちに設立したFC大阪の経営方針「サッカーを通じた地域社会への貢献」にも大きな影響を与えた。
サッカーに救われ、サッカークラブをつくる
ブラジルでの生活を終え、吉澤さんが次のキャリアに選んだのは会社経営だった。
「サッカーが縁で知り合った方からのお声がけで、会社経営に携わることになりました。もともと人の下について働くのは向いていないと思っていたので、案外すんなりと経営の世界に入っていけました。」
経営者として手腕を振るい、会社は順調に成長していった。ところがそんな折、吉澤さんを病魔が襲った。病状は芳しくなく、気分も暗く落ち込むように。順調だった会社も、別の人に譲らざるをえなくなった。そんなどん底の状況から吉澤さんを救ったのは、サッカーの存在だったという。
「たまたま、入院をしていた病院の目の前がグラウンドだったんです。週末になると社会人サッカーが行われていて、それを眺めるのが唯一の生きがいだった。やがて、看護師さんの計らいでそのチームの方々と交流が生まれるようになりました。病気がつらくても週末になったら彼らに会える、サッカーに関われるということが大きな励みになり、心身ともに回復していきました。あのとき彼らとの出会い、サッカーとの再会がなかったら、本当にどうなっていたかわからないです。」

病状が回復した後は、新たにスポーツ専門会社を設立した。そして1996年に社内サークルとして、サッカー部を創部。2006年からは、本格的にプロ化を目指しはじめた。
「自分自身がサッカーによって救われたので、サッカーで若者に夢を与えたいという思い
がありました。プロ選手になる夢が破れた若者に再びチャンスをつかめる場を提供したいと考え、プロ化を目指すことにしたのです。」
プロ化を目指してからは、実に14年の年月をかけ着実にステップアップ。2020年2月には「Jリーグ百年構想クラブ」の認定を受け、現在はJ3リーグ参入目前にまで到達している。
サッカーを通じた地域社会への貢献は、そのままSDGsにつながる
FC大阪がJリーグ入りを目指しながら、力を入れていること。それは、クラブの経営方針でもある「サッカーを通じた地域社会への貢献」だ。
「ブラジルだけでなくヨーロッパに目を向けても、サッカークラブは地域社会と深く関わり、地域の社会課題を解決するプラットフォームとして機能していました。日本でもサッカークラブは地域と密接に関わっていましたが、さらに一歩踏み込んでサッカークラブが地域の結節点になるべきだと考えました。試合がある日も無い日も、スタジアムに人や地域の情報が集まり、人と人、人と地域がつながるハブ的存在を目指すということです。FC大阪というコンテンツがその役割を担えるはずだと思ったのです。」

その思いや活動がSDGsと結びついたきっかけは、2018年から開始した大阪府との連携だという。大阪が2025年の万博会場候補地として選ばれたこともあり、大阪府としてのSDGsへの取り組みが加速していた時期と重なる。(2018年11月開催地決定)
「大阪府との連携で改めてSDGsの概念を意識してみると、それまで既に我々が行っていた活動がSDGsに結びつくものが多いことに気づきました。また、今後FC大阪で行っていきたいと思っていたことも、SDGsの項目の中にあった。それであれば、SDGsとして発信していった方が、伝わりやすいし啓蒙にもつながると考えました。」
つまり、新たにSDGsに取り組もうと何かを始めたというよりも、既存の活動や今後の活動をSDGsと結びつけてわかりやすく企画、発信することをスタートさせたのだ。
「我々をサッカークラブ運営におけるSDGsの先駆者のように言っていただくこともあるのですが、他のサッカークラブがSDGsに関連した活動をしていなかったということではないんですね。ただ、既存の活動をSDGsと結びつけられていないケースが多かっただけなんです。」
そのため、サッカークラブやさまざまなスポーツのチームからも問い合わせがあれば、オープンに情報共有をしている。FC大阪がスポーツチームにおけるSDGs運営のお手本になり、SDGsを啓蒙する役割を果たしているともいえるだろう。

連携先や選手とともに行うSDGs啓蒙活動
具体的にどのようなSDGs関連の取り組みを行っているのだろうか。紐解いてみると、自治体や企業、大学とパートナーシップを締結し、共同で行っている取り組みが多い。
「自治体や組織によって対峙する社会課題が違うので、それぞれに合わせた企画を実施することで、より課題解決につながる取り組みができると考えています。」
その言葉通り、連携先によって行う活動はさまざまだ。ホームゲーム開催時には、大阪府との連携により「SDGsスペシャルマッチ」を開催し、試合日ごとに異なるSDGsのテーマでイベント開催を行っている。また、株式会社アデランスとのコラボレーションでは、乳がん検診啓蒙を目的とした「ピンクリボン活動」として女子選手がピンクのヘアエクステンションをつけて試合に挑んだ。

阪南市と共同で海開き前のビーチで地域の人たちとゴミ拾いをし、サッカー教室を行ったり、大阪大学との産学連携プロジェクトにおいてSDGsのワークショップを行ったりと、スタジアム外での活動も盛んだ。
「どれも共通しているのは、選手が積極的に参画していることです。試合前のブースに立ったり、イベントに参加したりすることで、地域の人たちと交流しながらSDGsについて学び合っています。」

多彩な活動の中で特に力を入れているのが、子どもの貧困問題だ。
「日本で貧困というとピンとこない人もいるかもしれませんが、日本に住む子どもの7人に1人が"相対的貧困"(=その国の文化水準、生活水準と比較して困窮した状態にあること)だと言われています。大阪府内でもこの問題に直面している自治体は多いため、課題解決の一助となれるよう、積極的に活動しています。」
ホームゲーム開催時などに行う「FC大阪 こども基金」の募金活動、大阪府母子寡婦福祉連合会を通じたひとり親家庭の子どもを対象としたサッカー教室、門真市の「門真こども未来応援チャンネル」の運営サポートなどもその取り組みの一部だ。

テーピングの長さにまで気を配る
対外的取り組みだけでなく、クラブ内でもSDGsを意識した運営を行っているという。
「例えば、選手の体に使用するテーピング。トレーナーと部位の状態をきちんと共有することで、必要最低限のテープのみを使用するように徹底してもらっています。また、ゴミの仕分けなどもかなり細かく行っています。」

選手は日々の活動を行う中で自然とSDGsに対する意識を高め、自ら積極的に実践してくれているという。
「選手は発信する側になるわけですから、意識が変わってきていると感じます。地域の皆さんや子ども達との交流の中で学ばせてもらいながら、相互効果も生まれていますよ。」
象印とのパートナーシップ
象印との連携についてお伺いすると、吉澤さんから笑みがこぼれた。
「象印さんは、幼少期からとても身近な存在だったんですよ。家の中に象印さんの電化製品がたくさんあったし、なによりサッカーの練習には象印さんの魔法瓶を持っていってましたから。魔法瓶の中には母がレモン水を入れてくれていて、ちょっとした自慢でしたね。」
そんな象印を吉澤さんが改めて注目したのは、2019年開催の「G20大阪サミット」だ。
「G20へ来場する国内外のメディアや関係者に象印さんのステンレスマグが配布されましたよね。この出来事がきっかけで、世の中にマイボトルが一気に浸透した印象がありました。取り組みにとても共感したので、何かご一緒できたらなと思うようになりました。」
そして、FC大阪のスタッフからの働きかけで両社に縁が生まれ、2020年3月、SDGs推進に関するパートナーシップを締結するに至った。
パートナーシップ締結後は、さっそくFC大阪ファンクラブの特典として象印とのコラボボトルを導入。また、今後のホームゲーム開催時には「給茶スポット」の実験的設置なども行う予定だ。
「子ども達にFC大阪を通して象印さんを知ってもらいたいですね。そして、マイボトルをより浸透させていきたいです。」

ウィズコロナのサッカークラブ運営
今、サッカークラブを語る上では避けて通れないのが全世界を襲う新型コロナウイルスの影響。FC大阪は全国のサッカークラブの中でも早い3月中旬の段階で、活動自粛に踏み切った。
「サッカーは練習してこそ。早期の活動自粛は苦渋の決断でした。そんな中で一番に思い浮かんだのは地域の子ども達です。発信力のあるサッカークラブが活動しているのに、子ども達にサッカーや外遊びを我慢して、なんて言えませんよね。子ども達への責任も感じ、自粛に踏み切ったのです。選手はよくぞ理解してくれたと思います。」
なによりも地域に重点を置くFC大阪ならではの決断だ。では、今後ウィズコロナの世界で、あるべきサッカークラブの姿はどう思い描いているのだろうか。
「コロナを機に、サッカークラブ運営のICT化を加速させていかなければと考えています。例えば、スタジアムに行かずともリモートで応援できるシステムを確立するなど、サポーターや地域の人たちと双方向につながり合う仕組みをつくっていきたい。さらにリモートで応援してもらうためには、映像媒体のクオリティ、映像の親しみやすさをさらに上げていくことも重要です。地域経済とスタジアム、活動拠点との連携施策を考案、実行していきたいと思っています。」

地域にとってますます必要とされるサッカークラブに
最後に、これからのFC大阪が目指す方向性について語ってくれた。
「現在もさまざまな地域と連携してメディアを運営していますが、今後さらに発展させ、まるでローカルテレビのように、チャンネルをつけたら常に地域の情報が得られるような地域の人たちに役立つメディアをつくっていきたいです。メディアに限らず、FC大阪の持つコンテンツ、インフラは地域の方が自由に利用できるものになるべきだと考えています。そういった意味でも、ゆくゆくは地域の方からFC大阪の会長を選んでもらうのもいいですね。」
FC大阪は今後ますます多くの地域の人々が参画することで、地域に必要とされるサッカークラブへと成長を続けていくことだろう。そして、サッカーの枠に留まらない「地域インフラ」、「地域の公共財」として定着するのではないだろうか。その取り組みは、同時にSDGsの推進へとつながっていくはずだ。

吉澤正登(よしざわ まさと)
2006年 地域発展を目的にスポーツビジネス界に転身。FC大阪運営支援グループ会社設立。FC大阪をプロサッカークラブとして運営。大阪から3つ目のJクラブを誕生させる事を目的に株式会社アールダッシュ(セールスプロモーション会社)をはじめ株式会社FC、その他8社の会⻑に就く。2015年 JFL昇格全国リーグ参戦。2017年 一般社団法人FC大阪スポーツクラブ 会⻑兼代表理事に就任。地域社会課題解決に向けて専門法人を設立。2018年 FC大阪 東大阪市にホームタウンを制定。株式会社FC大阪 設立 会長就任。2020年 Jリーグ 百年構想クラブ認定。
*プロフィール、本文等、内容については2020年7月取材時のものとなります。