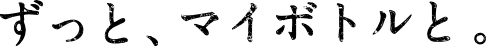COLUMN
2020.01.09
SpecialCOLUMN
未来へつなぐ、私のバトン
住宅を社会課題解決の一助に。 ロールモデルなき未来への挑戦。
積水ハウス株式会社 CSR部長 小谷 美樹

2019年6月、社内でのペットボトル使用ゼロ宣言を行なった象印。それに先駆けること半年、2018年11月に会議へのペットボトル持ち込み禁止を打ち出していた企業がある。象印と同じく、大阪市に本社を置く大手住宅メーカー、積水ハウスだ。
サステナブル社会の実現に向けた取り組みを推進するCSR部長を務めるのが小谷美樹さん。大阪で活躍する女性を顕彰する大阪商工会議所の「第2回大阪サクヤヒメ表彰」で大賞に輝くなど、女性活躍・ダイバーシティの推進にも積極的に取り組まれている。当時まだ珍しい女性の技術職、開発者としてキャリアをスタートし、その後、女性リーダーとしてロールモデルなき道を切り拓き続けている小谷さんに、住宅メーカー・積水ハウスとしての社会的責任について伺った。
女性技術者に希少価値を感じ、住宅設計の道へ
大学で建築を学び、中でも「住宅」に今後の自身の広がりや可能性を感じて積水ハウスに入社した小谷さん。男性が多い職場で、女性技術者というのは希少価値になるのではないかと感じたのが理由のひとつだと言う。
「入社後は設計の仕事に携わり、賃貸住宅『シャーメゾン』を100棟くらい設計しました。その後、結婚などを経て、研究開発職として本社に転勤することになります。それまでの、お客様一人ひとりに合った住宅を設計する仕事とは違い、研究開発という仕事は、全商品に入る基本技術の設計を担います。例えば、内装下地という、仕上れば見えなくなる床・壁・天井の基本部材の設計。断熱性や遮音性に関わる、住み心地にとって非常に重要な部分です。」

「そこで私は『省エネルギー住宅』という、断熱性・気密性の向上により省エネかつ快適に住まえるか、の研究開発から商品化に携わることになります。積水ハウスでは、北は北海道から、南は鹿児島まで、気候区分毎の設計をしていますが、北海道の札幌の住宅では、北国の厳しい自然に合わせた断熱・気密設計を行います。世の中の省エネの気運が高まるにつれ、この技術を全国に展開すれば、真冬でも快適で、省エネな住宅の設計ができるのではと思い、チームリーダーとして寒冷地の断熱仕様を全国に展開する構想を実現しました。自分のキャリアにおいて、ひとつの節目になったプロジェクトですね。」

女性リーダーとしてのロールモデルを切り拓く
「19年ほど、断熱に関わる仕事を担当し、2004年に本社で課長にして頂きましたが、事業所における女性リーダーの育成モデルとして、2012年に戸建て住宅の支店に異動し、積水ハウスとして当時全国で2人目となる女性の設計長(統括課長)を拝命しました。」
事業所から本社、本社から事業所と活躍の場を移しながら女性リーダーとしてのロールモデルを切り拓いてきた小谷さん。2014年には、新設されたダイバーシティ推進室で部長職として主に女性技術者の活躍推進に携わることになる。
「この様なお仕事をしていると『ロールモデルがなくて大変じゃないですか?』とよく聞かれるんですが、実はそのほうがやりやすい面もあります。初めてのことへの挑戦というのが好きなのですね。もちろん頭を打つこともありますが、それも経験です。やってみてダメだったら『こっちはダメだったな』『やり方を変えよう』という判断材料になるわけですから。」

「技術者という仕事において女性でいることは、その希少価値も楽しみながらやってきました。しかし、ロールモデルが少ないことや、建設業ゆえ、そもそも人数が少ない全国にいる女性が仕事を続けて活躍する方法を模索しながら、4年間、ダイバーシティの推進を担当しました。自分のキャリアや子育ての経験も含めて、女性技術職の推進や仕事と育児の両立支援など、当社の女性社員が能力を最大限に発揮し、いきいき活躍できる環境づくりに努めてきました。」

CSR部長に就任し、ESG経営を加速
そして、2018年。これまでの技術職としての経験、ダイバーシティ推進の経験をもって、CSR部長に就任。ESG経営(Environment:環境、Social:社会、Governance:ガバナンス、3つの観点に重きを置いたサステナブルな企業経営)の推進を担当している。
「ESGのEは『環境』を意味しますが、私自身がゼロエネルギー住宅の基本となる断熱設計の研究や開発に関わっていたこともあり、大変思い入れがあります。ダイバーシティをはじめとする女性活躍や働き方改革はSの『社会』に位置付けています。Gの『ガバナンス』は風通しのいい職場づくりそのものです。これらのESGは、これまでの経験がとても生きる仕事だと思っています。」

サステナビリティビジョンが見据える、2050年の社会の姿
積水ハウスではESG経営を進める上で、SDGsのゴールとなる2030年のさらに先、2050年のサステナビリティビジョンを掲げている。「脱炭素社会」、「人と自然の共生社会」、「資源循環型社会」、「長寿先進・ダイバーシティ社会」という、大きく4つの社会を目指すという宣言だ。
「その中の3つが、ESGのE、環境に関する社会です。『脱炭素社会』に向けては、これまで携わっていたゼロエネルギー住宅の事業が大きく関連しています。私が技術者時代に開発した断熱材による省エネ効果も一役買っています。太陽光発電、省エネ設備、給湯器などを組み合わせ、脱炭素の取り組みを進めているほか、事業活動において使用する電力を100%再生可能エネルギーにすることを目指す『RE100』イニシアチブに加盟しています。太陽光発電の電力会社による買い取り期間10年が過ぎたオーナー様の電気を買い取り、自社の事業に活用するといった取り組みも『積水ハウス オーナーでんき』として実施しています。」

住宅業界初の「エコ・ファースト企業」に認定
「次に、『人と自然の共生社会』についてですが、『5本の樹計画』というのがありまして『3本は鳥のために、2本は蝶のために』を理念に、住宅開発などで木を切り倒しても、その土地の在来種を新たに植え直すことで、鳥や蝶が戻ってこれるようにしよう、というメッセージを込めた取り組みです。土地固有の樹木をしっかりとその地域の中で使えるように、国内5つの気候区分から、地域ごとに適した樹木を選びまして、都道府県別の樹木提案も可能にしています。積水ハウスの本社が所在する新梅田シティの一角の公開空地に創設した『新・里山』では、在来種を植えて生態系を守る取り組みをしているんですよ。」

最後に説明いただいたのが「資源循環型社会」。積水ハウスは2008年、住宅業界として初めて、環境大臣から「エコ・ファースト企業」としての認定も受けている。
「結束バンドなど、プラスチック製の建築資材も多い中、これまでも、まず現場で27分別、さらに工場で82分別して再資源化するという取り組みをずっと実施してきました。そのほか、積水ハウス『エコ・ファースト・パーク』という体験施設を茨城県古河市に作り、そこでプラスチックの処理などを行いつつ、環境教育の場として一般にも公開しています。」

社内会議でのペットボトル使用を禁止に
海洋プラスチックごみの問題が日本でも大きく取り上げられるようになった2018年、積水ハウスは他社に先駆け、会議でのペットボトル使用を禁止することを決断した。環境省が進めている『プラスチック・スマート』のキャンペーンに賛同した取り組みだ。
「キャンペーンに賛同するだけでなく、社内の自動販売機からはペットボトルを無くすよう働きかけました。『マイボトル・マイバックキャンペーン』と呼んで取り組んでいます。当初は、やはり社員から『水が欲しい』『こういうときはどうするのか』といった問い合わせがありました。そうした声は想定していたので、あくまで強制ではなく、最終的な目標・方針であることを示し、理解を得ながら、徐々に進めていく形を取りました。当社は建設業のため、夏の現場の熱中症対策は重要です。強制はせず、ウォータータンクを設置するなど、各現場で対策を施しながら少しずつ進めています。」

「一人ひとりの意識が少し変わるだけで、一日に使うペットボトルが一本減る、二本減る。そういうことからまず始めていくことが大事です。じゃあ次に何ができるか、プラスチックのストローをやめてみよう、とか、それぞれが考えて行動に移してもらう。そのスタートがこれだ、ということなんです。」

社会課題に対して、企業としての姿勢を示すことが大切
積水ハウスでは、社長自ら『ESG経営のリーディングカンパニーを目指す』と宣言しており、中期経営計画にもESG経営が組み込まれている。社内に向けても様々な場面や切り口で伝えられている。すべてがその一環であることの理解は得られてきていると小谷さんは語る。
「世間がこれだけ脱プラに向かっている中で、会社として何ができるか考えることが大切で、しっかり方向性を示すことが必要。さらに当社では、方針が示されたあと、具体的にどうやるか、どう進めるかについては部署ごとに考えるという仕組みになっています。例えば、神奈川県で脱プラ宣言の取り組みがあれば、当社の事業所が賛同するなどです。大阪でもそういった地域の環境キャンペーンへの参加が進んでいます。会社が方向性を示すことで、各事業所が自発的に行動に移していく、という企業文化であり、その根本には当社の根本哲学『人間愛』があります。とても嬉しく、誇らしく思いますね。」

文化を支えるのも、企業の大切な使命
この日の取材は、積水ハウスの本社がある梅田スカイビルの27階に誕生した眺望抜群の最新型ミュージアム「絹谷幸二 天空美術館」で行われた。
「自社のメセナ活動のひとつとして、日本が誇る芸術家・絹谷幸二氏の美術館を2017年に開設しました。企業の地域貢献活動における重要なもののひとつに、文化を作るということがあると思っておりまして、芸術を通じた文化活動を行っていくことも積水ハウスの使命のひとつです。人々が生活していく上での心のビタミンと言いますか、単に器を作るだけではダメで、そこで営まれる暮らしや文化までを支えていくことが大切ですよね。」

世界一幸せな会社になるために
積水ハウスは「『わが家』を世界一幸せな場所にする」というビジョンを掲げている。同時に「積水ハウスグループ全体を世界一幸せな会社にする」ということにも力を入れていると小谷さんは語る。
「世界一幸せな会社にするためには、私らしく、自分らしく働ける環境というのが重要だと思っておりまして、LGBTにおいては同性婚にも手当などの制度を設ける取り組みを進めています。ダイバーシティの推進によって、多様な人材がどんどん増えていきますし、定年が引き上げられ、高齢社員も増えるなど、年齢の幅も広がります。多様な社員同士がコミュニケーションしやすい職場づくりがますます重要になりますね。」
「在宅勤務も推進していますが、そうした取り組みは急にはできません。最初は一人の社員の声から始まることもあります。まずはその社員からトライアンドエラーでやってみようと。試行を繰り返して、いよいよ制度に、という進め方ですね。お客様一人ひとりに向けて個別に住宅提供する会社ですので、社内向けの施策も、まずは一人の社員からやってみようということになります。試行錯誤して、次の施策に繋げていくという企業文化なんです。」

住宅は社会課題解決の一助になる
ESG経営、サステナブルな取り組み、と口で言うのは簡単だが、社内の取り組みだけでなく、実際に事業にまで落とし込んでいくことは難しい。それを実現させていく強い意志はいったいどこから生まれてくるのだろうか。
「住宅が社会課題解決の一助になると考えていることが、私たちのモチベーションの源泉になっています。例えば、太陽光発電はエネルギー問題を解決しますし、資源の循環や廃棄物の削減にも寄与できる。住宅というのはかなり社会的側面の強い産物ですから、高齢者に配慮した住宅を建てれば高齢化社会への一助になりますし、子育てしやすい住宅を建てれば、少子化対策にも貢献できる。当社の住宅を選んでいただくことが、お客様にとって一番の社会貢献になるような、そういう住宅のあり方を考え続けていきたいですね。」

2025年にはSDGs万博とも言われる大阪万博が控えているが、さらにその先の2050年のビジョン実現に向けて、全社的にSDGsに取り組んでいる積水ハウス。「全社ということは全国各地のエリア事業所までを意味しますので、ここ大阪から全国に、しっかりと広げていきたい」と最後に語ってくれた小谷さんの前例なき挑戦は、まだまだ続いていきそうだ。

小谷美樹(こたに みき)
1988年積水ハウスに技術総合職として入社。住宅設計や内装、省エネ開発などを担当。結婚・出産後本社技術本部に勤務。開発部課長、女性設計長を経て、2014年経営企画部ダイバーシティ推進室部長へ。2018年同社CSR部長に就任。一級建築士。
*プロフィール、本文等、内容については2019年11月取材時のものとなります。