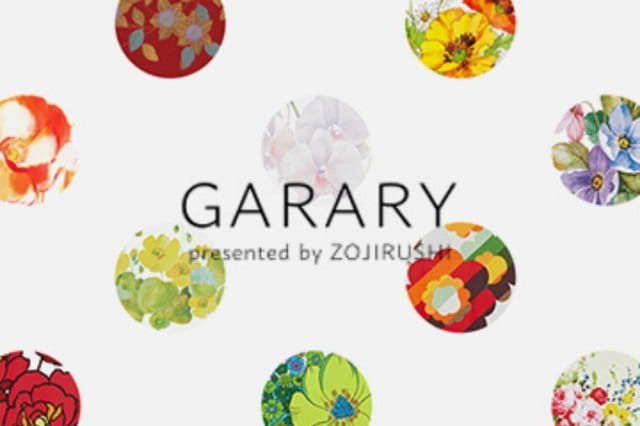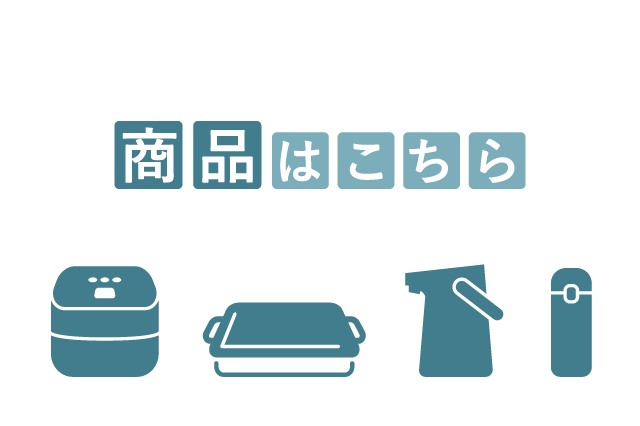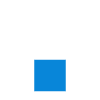
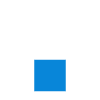 ごはん+
ごはん+
おかゆの効果とは?基本の作り方とおすすめのレシピもご紹介!

おかゆというと「体調不良のときに食べるもの」というイメージがあるかもしれませんが、最近の健康志向の高まりで、少しずつそのイメージが変わりつつあります。各メーカーのおかゆ関連の商品ラインアップが充実しており、普段の食事に取り入れているという方も多いのではないでしょうか?そこで今回は、おかゆの効果や作り方、レシピについてご紹介します。
おかゆの効果とは?注意点もご紹介
おかゆの効果
おかゆの効果は古くから伝えられており、曹洞宗の開祖である道元(鎌倉時代の禅僧)が記した書物「赴粥飯法(ふしゅくはんぽう)」では、おかゆの効能を「粥有十利(しゅうゆうじり)」という言葉で以下のようにまとめています。
【粥有十利(しゅうゆうじり)】
- 色 :肌の色艶をよくする
- 力 :気力が増す
- 寿 :寿命が延びる
- 楽 :食べ過ぎになることがなく、体が楽になる
- 詞清辯(ししょうべん) :血流がよくなり頭が冴え、言葉もなめらかになる
- 宿食除 :胸やけをしない
- 風除 :風邪を引かない
- 飢消(きしょう) :飢えを満たす
- 渇消 (かっしょう):喉の渇きを潤す
- 大小便調適 :便通がよくなる
おかゆのデメリットや注意点は?
おかゆにはさまざまな効果・効能があると言われていますが、それだけだとカロリーや栄養素が不足してしまいます。おかゆを普段の食事に取り入れるときは、副菜や主菜を準備してカロリーや栄養バランスを補いましょう。また、おかゆといえども噛まずに飲み込むと消化吸収に時間がかかり、胃腸に負担を与えてしまいます。消化不良の原因になるため、しっかり咀嚼してから飲み込むようにしましょう。
水分量で変わる!おかゆの種類とは?
おかゆの種類
おかゆには、炊き粥と入れ粥の2種類があります。炊き粥は、お米から炊くおかゆのこと、入れ粥はごはんに水を足して炊くおかゆのことです。
おかゆの水加減
おかゆは水の量によって、以下のように呼び方が変わります。
- 全粥(ぜんがゆ) お米1:水5
- 七分粥(しちぶがゆ) お米1:水7
- 五分粥(ごぶがゆ) お米1:水10
- 三分粥(さんぶがゆ) お米1:水20
- 重湯(おもゆ) お米に対して10倍程度の水でお粥を炊いたときにできる上澄み液のこと
おいしいおかゆの作り方

お米から炊く「炊き粥」の作り方をご紹介します。
- お米を軽く洗う
- 洗ったお米はザルにあげ、水気を切っておく
- 鍋にお米と好みの分量の水を加え、フタをして強火で沸かす
- 沸騰したら弱火にしてフタを少しずらす
- 弱火のまま30〜40分煮る
- 塩ひとつまみを加えてから火を止め、底の方から軽くかき混ぜる
上手に作れる自信がない……という方は、炊飯器のおかゆメニューを利用するのが便利です。より簡単においしく作ることができるのでせひ試してみてください。
おかゆをおいしく簡単に調理!象印のおすすめ炊飯ジャーをご紹介
圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」 NW-FC10・18

- 縦横無尽にお米を舞い上げ、大粒でふっくら甘みのあるごはんに炊き上げる「3DローテーションIH構造」
- 炎舞炊きの集中加熱を活かす「鉄(くろがね仕込み)豪炎かまど釜」
- 銘柄や季節に関係なく、好みの食感に調整できる!121通りの「わが家炊き」メニュー
- 料理やその日の気分に合わせて15通りから選べる「炊き分けセレクト」メニュー
- 芯まで甘くやわらかい「おかゆ」メニューと、ごはんの粒立ちが感じられ、さらっと食べられる「粒立ちがゆ」メニューがあります。
「粒立ちがゆ」メニューでできる!おすすめのおかゆレシピ
通常の「おかゆ」メニューよりも粒感があり、日常食として食べやすいメニューです。
ぜひ「粒立ちがゆ」メニューのアレンジレシピでおいしく楽しく、おかゆをお楽しみください!
鮭と明太子のおかゆ
韓国風キムチがゆ
チーズオムライス風がゆ
まとめ
今回ご紹介した基本の作り方でシンプルなおかゆを作るのもよいですが、栄養バランスを整えたり、食べ応えを出したりするには、具材を加えるのもおすすめ。普段の食事におかゆを取り入れたいという方は、ぜひおかゆレシピも参考にしてみてください。
この記事で紹介された
アイテムの購入はこちら
この記事を書いた人

ZOJIRUSHI編集部
「暮らしをつくる」を企業理念として、お客様に快適で便利な家庭用品を提供しているZOJIRUSHI編集部