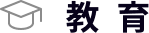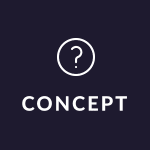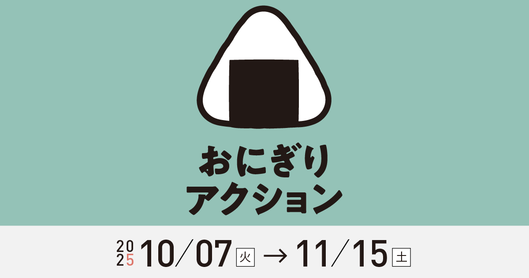象印マホービンは、日本の田んぼを守る「水田オーナーズクラブ」の活動に2014年から賛同しており、地域の方々の協力を得ながら鳥取県日野郡の田んぼで「象印農園米」を育てています。
8月の作業内容
残暑が厳しい時期ですが、お盆の頃に降った雨のおかげで田んぼはたっぷりと水を含み、稲穂も順調にふくらんでいます。町内には水が足りない田んぼもあったため、改めて雨のありがたさを感じておられるとのことです 。
8月に入ってから、ドローンを使った害虫防除作業や害獣対策の電気柵の点検、草刈りなど、稲刈りに向けての準備が進められています。稲の穂が出揃う「出穂(しゅっすい)」の時期を迎え、その後、稲穂にお米の花が咲き、受粉した籾が成長していきます 。現在、稲穂は色づき始め、新米の季節がもうすぐそこまで来ています。
①出穂
茎の中から、さやを割ってうす緑色の穂が出てきます。この穂にお米の花が咲き、受粉した籾(もみ)がお米へと成長していきます。

②登熟
受粉した籾は、光合成で作られたブドウ糖が酵素の働きによってデンプンに変わり、少しずつ実っていきます。

③高温障害と夜間気温
デンプンの籾への蓄積は夜間に行われます。ところが、夜間気温が高いと稲の呼吸が活性化し、デンプンをエネルギーとして消費してしまうため蓄積がうまくいかなくなり、未熟粒になってしまいます。

④イネカメムシの防除
近年、イネカメムシによる斑点米被害が増加しています。要因として、地球温暖化による成虫の越冬成功率の上昇、繁殖サイクルの短縮化などが挙げられています。現在、農協や自治体が、発生予測や防除方法の情報提供を強化しています。

※本記事の内容は、掲載日時点の情報です。